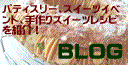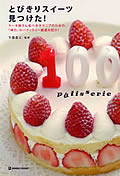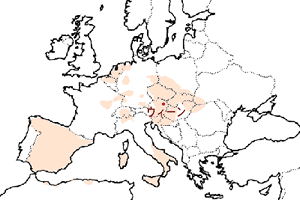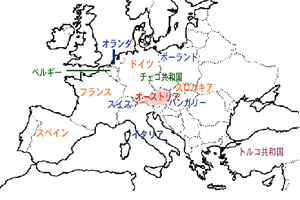【ウィーン菓子とハプスブルク家の歴史について】
ウィーン菓子について調べていくと、ハプスブルク家の歴史と深く関わっていることが分かってくる。
「ハプスブルク家」は13世紀後半から19世紀はじめまでの640年間という驚くほど長い間オーストリアを中心に統括していた王家である。
ハプスブルク家は、戦いではなく結婚政策によって他国と縁組みしては、次々に領土を拡大していった。その勢力は「陽の沈まない帝国」と表現されたほど強大だった。
ハプスブルク家が長い歴史の中で納めた国は、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランス、イタリア、スペイン、ハンガリー、チェコ、スロバキア、旧ユーゴスラビア、ポーランド、ロシアやルーマニアの1部などといった非常に広範囲の領土を所有してきた。
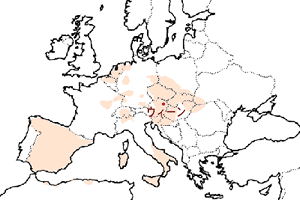 |
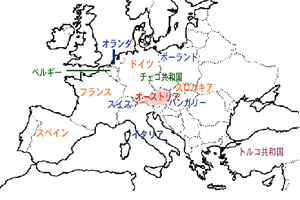 |
| ▲16世紀前半のハプスブルク家の領地。王家間の結婚政策によって領土を広めていった。 |
▲現在のヨーロッパ地図。(比較資料) |
そのため、オーストリアの中心ウィーンには各国の食文化が伝わった。
例えば、クヌーデル(だんご状の料理、お菓子)はボヘミア地方(チェコの西部・中部地方)、トボストルテはハンガリー、シュトゥルーデルはトルコから伝わったと言われている。各地から伝わった菓子は当時は素朴なものだったようだが、ウィーンの菓子職人達によって優雅なお菓子へと形を変えていった。
 |
|
 |
|
▲グリースヌーデル。グリース(粉)以外にもジャガイモやトプフェン(チーズ)を使ったクヌーデルなどもある。
|
▲ドボストルテ。薄く焼いた生地とチョコレートクリームのバタークリームを層にして重ねる。 |
▲アプフェルシュトゥルーデル。薄くのばした生地に詰め物をしたお菓子。本国ではリンゴ以外にも色んな種類のシュトゥルーデルがある。 |
また、甘い物好きなハプスブルク家の人々(女帝マリアテレジアやその末娘マリーアントワネット、最後の皇帝フランツヨーゼフ1世など)の存在もウィーン菓子の発展に貢献したと言われる。
ウィーン菓子が現在の形になったのは、1814〜1815年に開催されたウィーン会議の頃だと言われている。
フランス革命、ナポレオン戦争後のヨーロッパの秩序を回復するため戦争参加国の政治家や要人がウィーンに集まった。この会議自体は各国の意見が衝突しなかなか進展することはなかったが、その一方毎日のように舞踏会、演奏会、祝宴が開かれた。そこで、各国からの賓客をもてなすために様々な優雅なお菓子が考え出された。
第一次世界大戦の最中、1916年ハプスブルク家最後の皇帝フランツ・ヨーゼフが死去し1918年にハプスブルク家の歴史が幕を閉じた。それから第二次世界大戦が終わるまではウィーン菓子の低迷期が続いた。
【ハプスブルク家没後〜現在】
その後ウィーン菓子が脚光を浴びたのはマイスターの「カール・シューマッハ」氏の登場だ。
カール・シューマッハ氏は伝統的な部分を残し、甘さや軽やかさなどを現代の人々の嗜好にあうような新しいウィーン菓子を作りだした。
現代のオーストリアでは、昔のような砂糖が富を表す時代ではないことや健康を気にする人も多くなったことから、全体的に甘さを控え食べ口の軽いお菓子が増えてきている。また、フランス菓子の影響で、フルーツを使ったり、色合いが柔らかいお菓子が登場している。
※カール・シューマッハ氏 1934年生まれ。1974年にオーバーラーのチーフになる。引退するまでの20年間数々の賞を受賞。ウィーン菓子の第一人者として世界的に有名。
 |
 |
 |
| ▲オーバーラー外観 |
▲オーバーラーのトプフェンシュトゥルーデル |
▲オーバーラーのショコラ |
<参考文献>
マイスターのウィーン菓子 八木淳司著 柴田書店
ケーキングvol.2 柴田書店
ハプスブルグ家 江村洋著 講談社現代新書
ハプスブルグ帝国 加藤雅彦著 河出書房新社